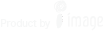日本の塩の歴史を分けて紹介している第2回目は、日本の製塩の技術についてお話ししたいと思います。
1000年以上続いた塩田の製塩

現在のイオン交換膜を利用した製塩法が開発されるまで、塩田による製塩は1000年以上も続きました。日本は島国のため、塩は海水を煮詰めて作るしかありませんでした。 さて、その海水を煮詰めるとき、気になる点が2つあります。 煮詰める時に使う火(燃料)とたくさんの海水を鍋に運ぶ労力です。
なるべくなら火をおこす時間が少ない方がいい(燃料が少なくてすむ)。また、水は非常に重いもの、どうせなら少ない回数で済ませたい…そんな思いから、塩田は生まれました。 要するに日本の塩田は、塩を作るのではなくて、海水を濃くする手段として作られたのです。
2種類の塩田



日本の塩田では海水の汲みあげ方により2つの方法がありました。揚浜式と入浜式です。 「揚浜式塩田」は、今から1200年位前の平安時代に考案された塩田です。 海水が漏れぬよう粘土で固めた平らな床の上に砂をまき、そこに海から桶でくみ上げた海水をひしゃくでまくと、砂の表面に付着した海水の水が太陽と風で蒸発し、表面に塩が残ります。その塩の付いた砂を寄せ集め、その砂を海水で洗い流すことにより濃い海水を得ていました。まるで風が吹いたら桶屋が儲かる風ですが、他によい方法がなかったようで、濃縮に砂を使う方法は昭和になるまで続けられました
この方法は今でも能登半島で(観光主体ですが)行われています(参考URL)。
しかし、塩分が3%しかない海水を桶でくみ上げる仕事はあまりにも大変でした。そこで海の干潮を利用して海水を塩田に引き入れる方法が考えらえれました。この方法を「入浜式塩田」と言い、500年位前(室町時代末期)から昭和30年頃まで続けられました。
この自然の力を利用した大変合理的な方法は、干潮と満潮の差が大きい瀬戸内海沿岸で開発・発展しました。江戸時代中期には瀬戸内海沿岸のほぼ全域にあたる十州で塩作りが栄え,現在でも日本の塩作りのメッカとなっています(お塩のメーカーが瀬戸内海沿岸に多いのはここに由来します)。
このように、自然と向き合って効率よい方法で日本の塩業は成長してきました。 しかし、天候により製造が左右されてしまう塩田を用いた方法は、効率はよくなっても重労働である事には代わりがありませんでした。
それを打破し、もっと効率よく精度の高い製塩法が開発されました。それが現在の塩製造の主流となっている「イオン交換膜製塩法」なのです。 次回は、その辺をお話ししたいと思います。 ※ 十州とは昔の地名で、播磨、備前、備中、備後、安芸、周防、長門、阿波、讃岐、伊予のことで現在の兵庫県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県愛媛県にあたります。


 塩のまめ知識
塩のまめ知識